- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
- English
- Japanese
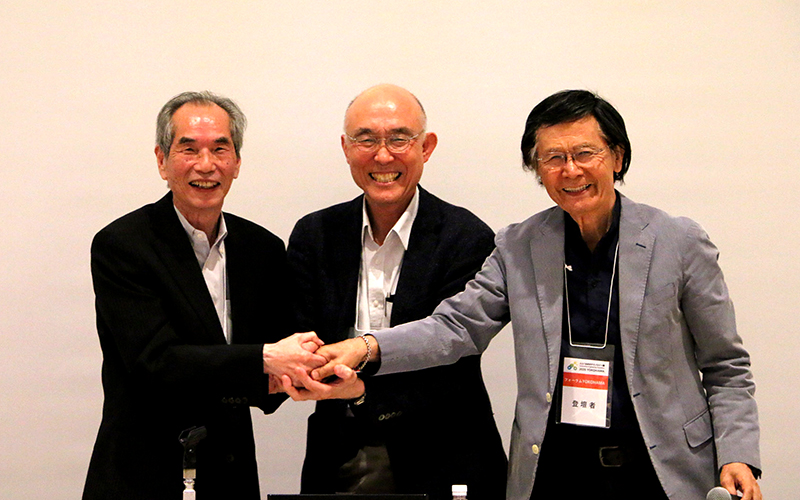
5月21日に開幕した自動車技術会主催の「人とクルマのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」(23日まで)で『モータースポーツフォーラム「モータースポーツ技術と文化」』が、初日の午後に開催された。そのフォーラムの最後には、SUPER GTが昨年30周年を迎えたことを記念した特別企画「スーパーGT三国志」と題したパネルディスカッションが行われた。
自動車技術会は会員(関連メーカーや技術系の学生や研究者)を招いた「自動車技術会フォーラム」を定期的に開催しているが、その中には『モータースポーツ技術と文化』と題したシンポジウムもある。
今回もトヨタ自動車株式会社の川喜田 篤史氏がGRヤリスを例に「モータースポーツに貢献する生産技術」と題してGRファクトリーでの競技車両開発と生産技術の関係性を発表。続いてホンダモビリティランド株式会社の古田 辰史氏が「鈴鹿サーキットのサステナビリティ経営に向けて」として、F1開催で求められるカーボンニュートラルや環境配慮への実践や単なるゴミのリサイクルではない観客や場内販売業の各社や地元団体も巻き込んだサステナビリティ施策を報告。そしてJAFの上村 昭一氏による「JAFのE-SPORTS取り組みについて」の現状紹介が行われた。

そして150名ほどの自動車技術者や学生、モータースポーツ関係者を集めたプログラムの最後に、SUPER GTの30周年を記念したパネルディスカッション「スーパーGT三国志」として、1990〜2010年代とSUPER GTや国内モータースポーツで活躍されたお三方を招いてのトークが実施された。
パネリストは全日本GT選手権(JGTC)のスタート当初から日産自動車/NISMOの中心として活躍された柿元邦彦氏、トヨタ自動車でJGTCのレース車両開発を担っておられた柘植和廣氏、HondaでF1やJTCC(ツーリングカーレース)などレース関連開発を行いJGTCのNSX開発リーダーであった田中尋真氏が招かれた。

まず、NISMOの総監督も務めた柿元邦彦氏がJGTC発足の経緯と当時の時代背景を説明。1990年代はバブル景気の崩壊が進みつつある中、グループC(プロトタイプカーによる耐久レース)やグループA(ツーリングカーレース)では強い車種や勝てる車種の傾向が収斂してカテゴリーの衰退に繋がっていたと語り、1992〜93年に日本のモータースポーツ界はどうあるべきかと迷う中で「特にNISMOはグループCやグループAが(事業の)柱であったため、これらがなくなったら困る。その時、『今あるクルマでできるレースを作ろう』と(国内モータースポーツ界に)呼び掛け、GTAが出来たわけです」と語った。「一方で勝てる車種の片寄りを防ぐためのウェイトハンディ(現在のサクセスウェイト)制や、様々な車種で多くのチームが参加でき、カテゴリーの継続性を図るために性能調整、BoPといった仕組みを取り入れました。あとクラスが複数あると観客が追い抜きシーンを多く楽しめはずと2クラスの混走となりました。これらが今も続いてSUPER GTは盛り上がっており、BoPは多くの世界選手権でも当然に使われております。でも当時、その仕組みは業界にはノーマルに受け止められず『プロレスのようなレース』と非難もありましたね」と、SUPER GTの原点を解説した。
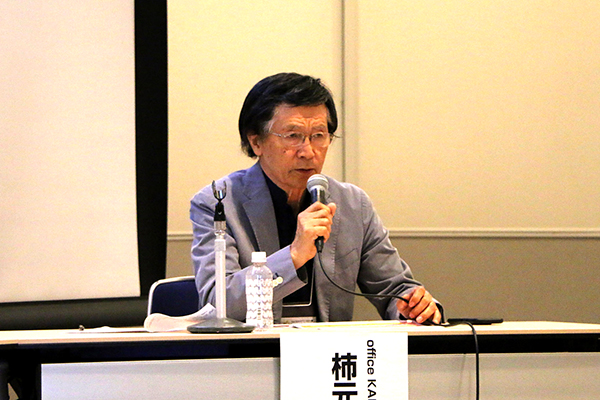
元日産/NISMO総監督の柿元邦彦氏
続いてHondaでF1プロジェクトやグループA車両、そしてJGTC/SUPER GTの車両開発に携わった田中尋真氏が紹介され「(JGTC参戦前には)Hondaは1.6リッターのCIVICでグループA、JTCCをやっていて、これが上手くいっていないということで、私にも声が掛かりました。レースの現場に行ってみると、もうメーカー間でドンパチ、かなりのしのぎの削り合いをやっていて(苦笑)、メーカー関係者間では挨拶も目も合わさないくらいでしたね。で、JGTCの構想が出たときは、FIAの規定やメーカー(の思惑)に頼らないレースにしたいと説明されて。実際に(Hondaが参戦を始めたときも)『メーカーのウェアを着てこないで』と言われて、私服で出掛けてチーム(のピット内)で椅子だけ借りて片隅にいました(笑)。でも技術の面から言えば、確かにBoPはあるけれど、車両の改造の範囲が大きいから、ここで差を出せればと思いましたね」と、当初のメーカーの立ち位置を教えてくれた。
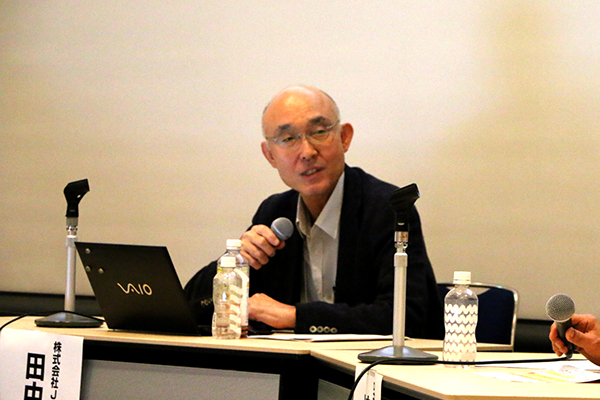
元Honda GTプロジェクトリーダーの田中尋真氏
同時期、トヨタ自動車でレース車両開発を行なっていた柘植和廣氏は「当時、TOYOTAはグループCをやり、その後はル・マン24時間でGT1車両を走らせましたが、それも終わりとなり、国内ではJGTCに出たいというチームの要望もあり、カスタマーサービスとして、JGTCのGT500クラス車両としてスープラ(初代)を開発しました(1994年の終盤2戦に1台が参戦。翌年から本格参戦)。1997年には全6戦中、5戦で優勝といい結果が出たことと、もうひとつHondaさんとやり合っていた(笑)JTCCが1998年に終わったので、JGTCにシフトしていったという流れです」と、JGTCへのスープラ参戦の経緯を説明した。

元トヨタ自動車 GT担当リーダーの柘植和廣氏
さらに柘植氏が、その翌年の1997年からHondaがNSXで本格参戦を開始したことに「TOYOTAも日産も身構えましたよね、柿元さん」と振ると柿元氏は「GT-Rも順風満帆ではなく、直6エンジンを前に積んでいたため、フロントヘビーで苦労しました。2001年は(直6から)V6エンジンにして、もっと前後重量配分を改善しようとラジエーターを(リアの)トランクルームに入れたんです。そしたら冷えなくてファンも追加して…、でも全然効かないので1年で止めました(苦笑)」と明かした。
またHondaの田中氏は「(参戦当初は)ミッドシップが有利だとまことしやかに言われまして(ハンデ等が積まれ)。アルミボディの加工も難しく、GT-Rとは逆にテールヘビーで悩んでいました。またエンジンへの空気取り入れも自然吸気ゆえに苦労していまして」と言うと、柿元氏からは「『ちょんまげ』を認めたじゃないですか(笑)」と、2002年からNSXで採用されたルーフ上に飛び出た吸気デバイスの話題を柿元氏が突っ込むと、「最初はルーフやサイドに40mmの薄いものを使っていましたが、これでもリストリクターも効かない程度の空気しか入らず、しかも市販車の車検が通らなくなって。しょうがないので標準装備の1つということで、あの『ちょんまげ』をNSXのType-Rのバリエーションで追加したんです。でも、市販車の方は吸気には関係ない飾りでして、カーボン製で80万円もしましたから1つも売れずに(生産の)管理部門から苦情を頂きました(苦笑)。でも20馬力上がりましたね。もちろんリストリクターの範囲内ですから、それだけ吸えてなかったんです」という思わぬ裏話に、150名ほどの参加者は自身も技術者や自動車業界志望の学生だけに感嘆の声も上がっていた。

この後も、各メーカーのGT500車両の排気量の変遷やレギュレーション制定の意義とそれぞれの駆け引き、さらにはこの3名がJAFや協会の要職に就いて起こったSUPER GT周辺の裏話など、1時間弱のディスカッションは非常に濃厚で興味深く、また笑いも絶えないものとなった。
